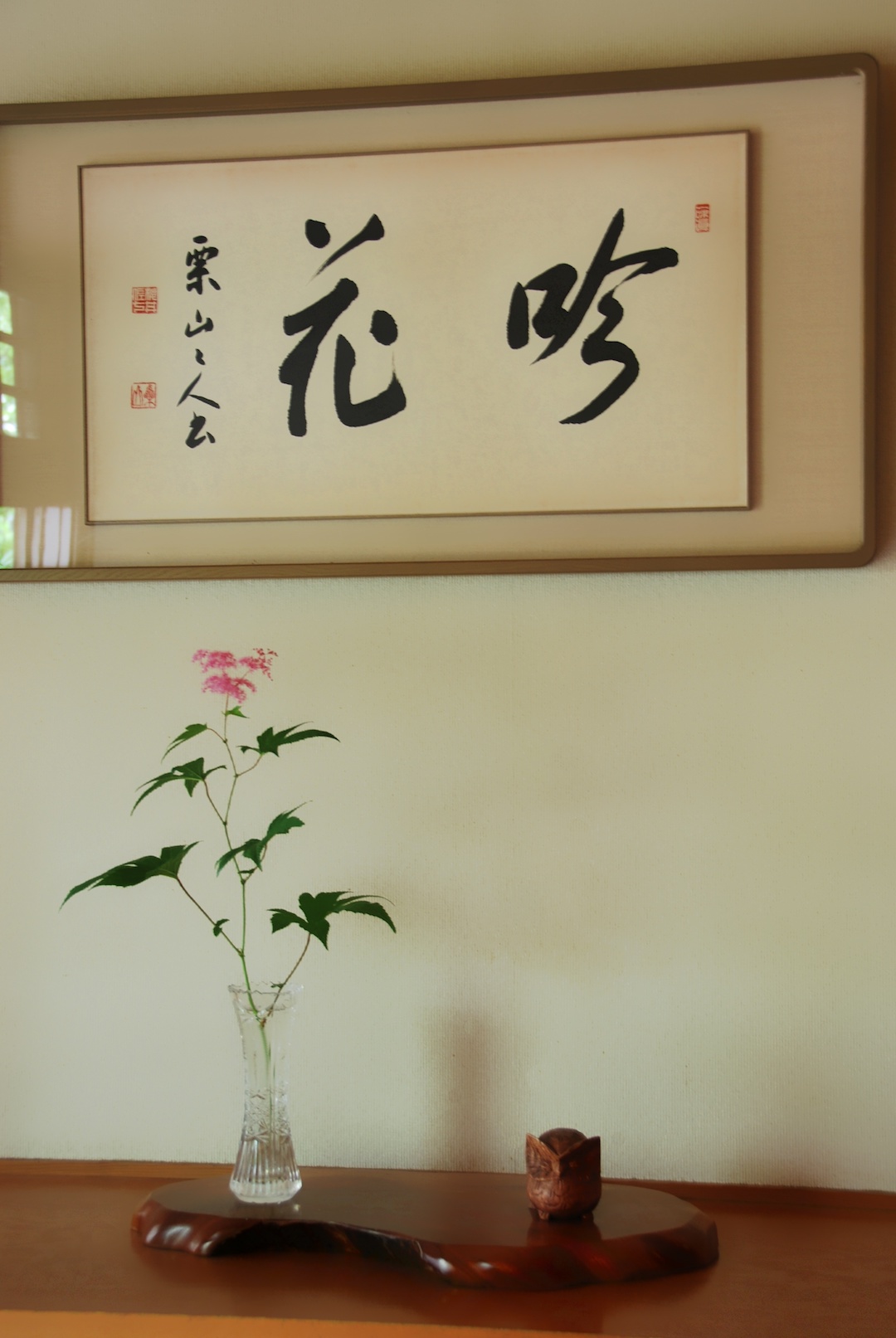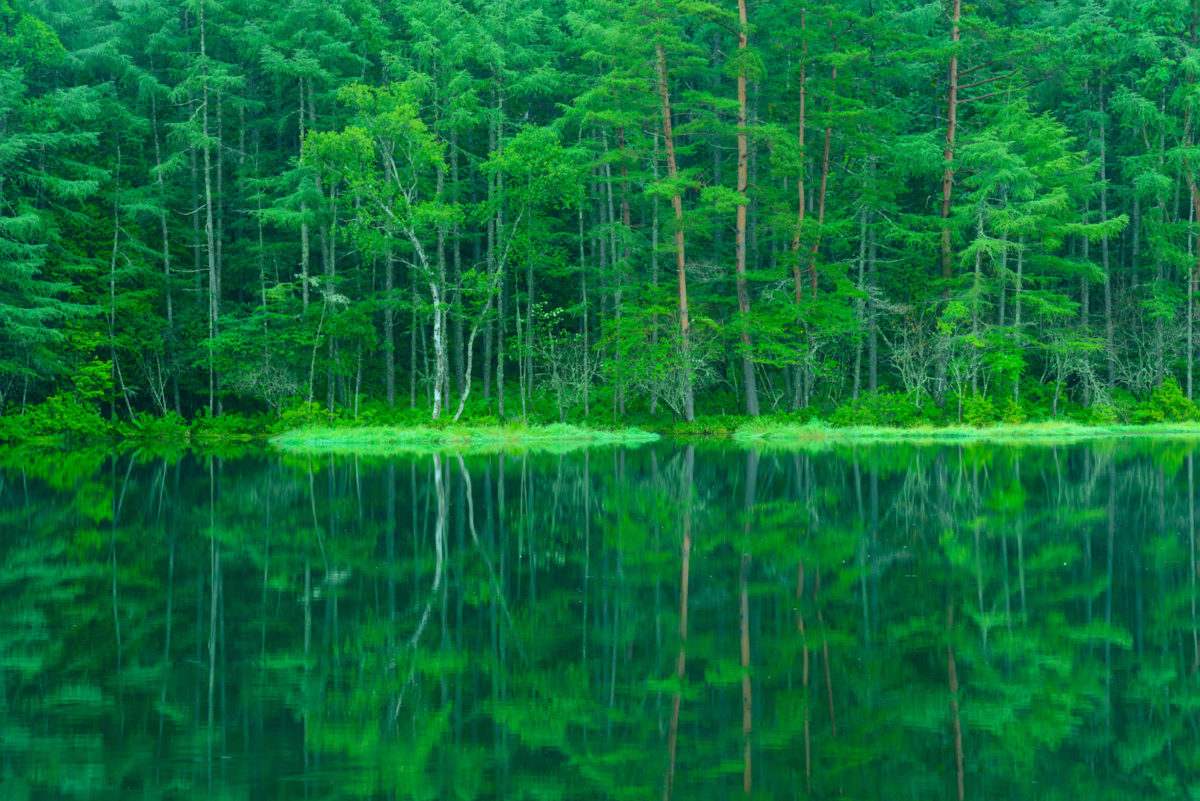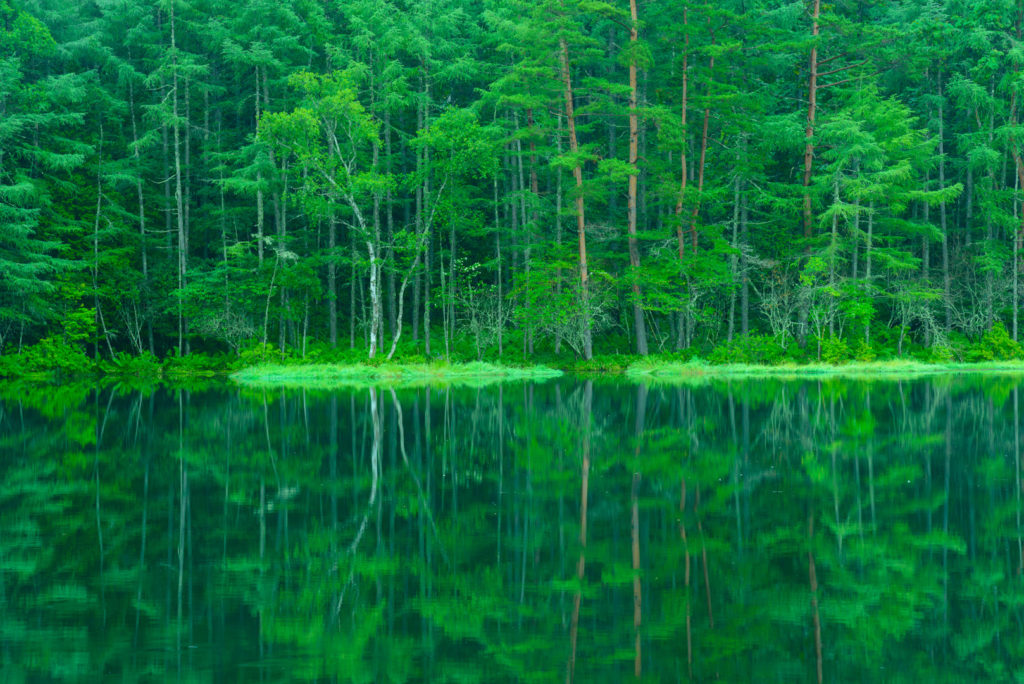こんにちは! プロ御用達の《古美術専門オークションサイト》サムライオークションです。
サムライオークションでは、9月7日(土)から、2020年2月末日までの6ヶ月間、落札手数料を無料にする【開設記念キャンペーン】を実施しています!
通常は出品者の皆さんから、落札価格の【2.16%】いただいている販売手数料を、半年間無料にするというキャンペーンです。
どう考えてもおトクじゃないですか?!
サムライオークションは、ファンの皆さまに骨董・古美術品を楽しんでいただくために、質の良い魅力的な、そして夢のある作品がサイトへ多数出品されることを願っています。
そしてサイトを訪れた方が、多くの作品を見て、比較して、自らの美意識に合う、自分が美しいと思う作品と出会えること、それがサムライオークションのミッションです。
サムライオークションでは、出品いただいた商品の落札が決まった場合、ユーザーの皆さんの売買取引に対するサポートサービスをご提供いたしますが、それに関わるサムライオークションの手数料は、キャンペーン期間中は一切必要ありません。半年間という期間限定ではありますが、オークションサイトの無料開放となります。
古物商の皆さまには、まずはサムライオークションへご登録・ご出品いただき、サムライオークションのサービスをお試しいただきたいと思います。
仕入れた商品のマーケティングツールとして、あるいはネット販売とはどんなものかというお試しツールとして、サムライオークションはただ今ノーコストですから、お気軽にスタートできると思います。
また、プロの骨董・古美術事業者様以外でも、趣味でコツコツとお品を蒐集している個人の方も、古物商免許をお持ちでしたら、この機会にぜひサムライオークションをご活用ください。これからもどうぞご贔屓に!