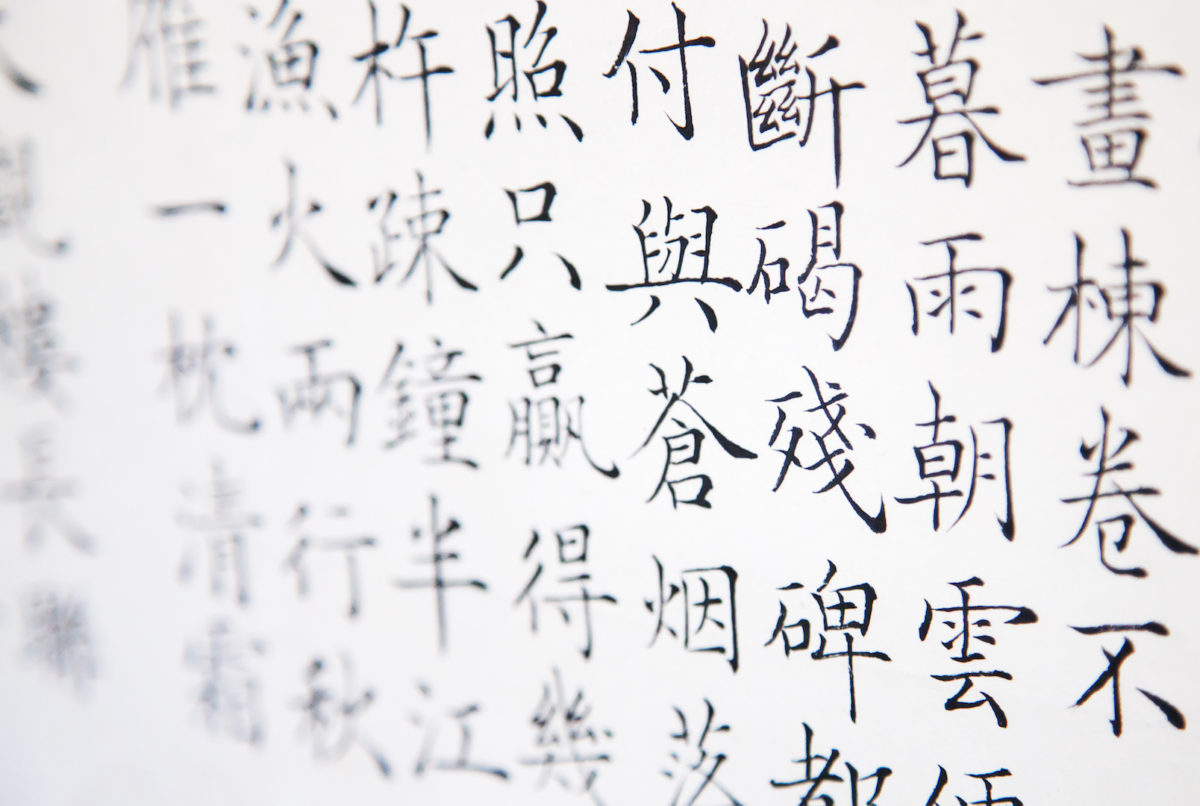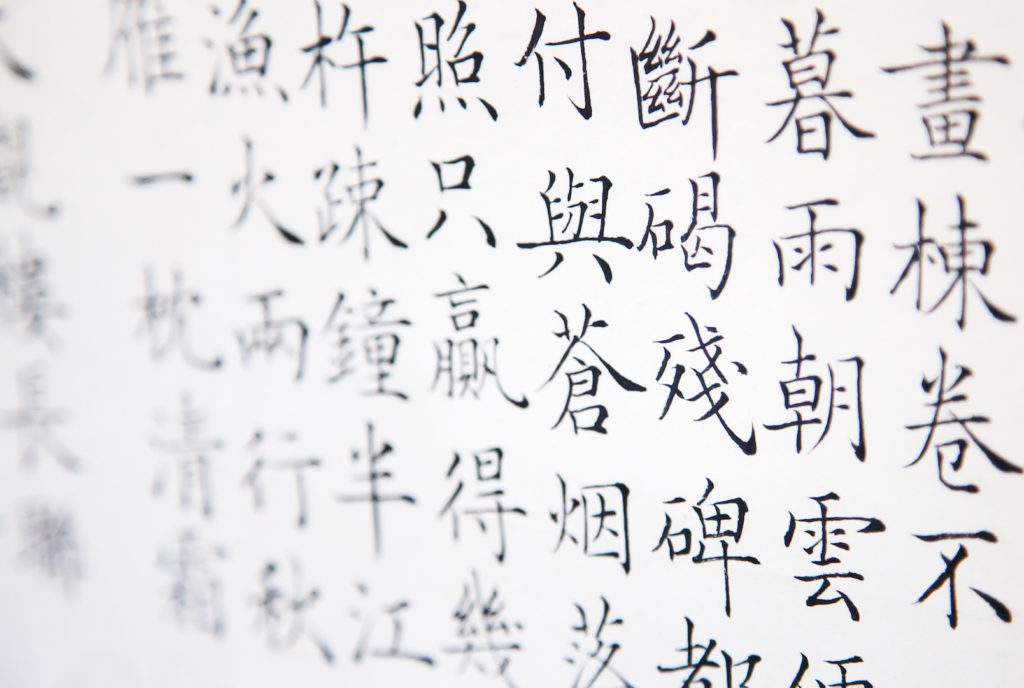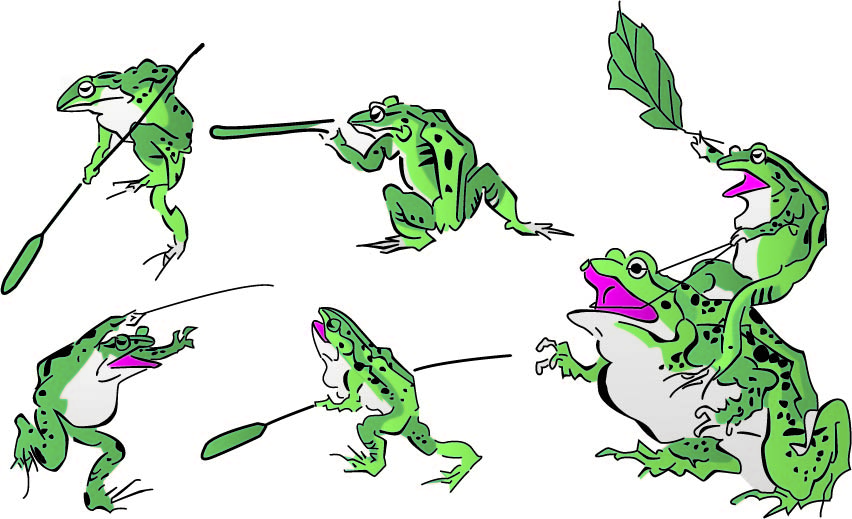こんにちは! 骨董・古美術ファンのための《古美術専門オークションサイト》サムライオークションです。
サムライオークションを訪ねてくださる皆さん! もうご存知かもしれませんが、その日は私もだいぶ興奮しましたので、ぜひこの気持を共有させてください。
10月28日にAFP通信発で世界に配信されたニュース
《仏住宅の台所で見つかったチマブーエの絵画、29億円で落札!》です。
チマブーエ(本名はチェンニ・ディ・ペーポ/1240年頃〜1302年頃)は、13世紀イタリアにおける最も偉大な画家の1人と言われています。ヴァザーリ(1511〜1574年/画家・建築家)が著した西洋美術史の重要な基礎資料《美術家列伝》では、最初に記されている画家であり、イタリアの詩人ダンテの《神曲》でも『絵画の世界の覇者』と表現されているほど、イタリア絵画の創始者として重要視されているアーティストです。
一節には世界に11点しか存在していないといわれているその画家の貴重な絵画が、フランス北部の一般家庭の台所で、ガスコンロの上に飾られていたのだとか。所有者の女性は、作品の来歴を知らず、ほとんど価値のない古い宗教画だと思いこんでいたようです。
オークション関係者がこの画を見つけ、鑑定に出すように持ち主に勧め、赤外線鑑定を行った結果、チマブーエの作品と判断されたそうです。発見された画のタイトルは《軽蔑されるキリスト》。この作品は祭壇画の連作として制作され、ロンドンのナショナル・ギャラリーに1幅、ニューヨークのフリック・コレクションに1幅が残されています。
オークションを手掛けたアクテオン・オークションハウスでは、当初600万ユーロ(約7億2600万円)程度での落札を予想していたそうですが、予測の4倍2400万ユーロ(約29億円)で落札されました。中世絵画の落札価格としては史上最高値のようです。
現時点での、海外ニュースメディアの報道では、持ち主がこの絵画をどのように入手したのかは書かれていないのですが、フランスの庶民的な地区で開催される蚤の市で『5千円くらいで買いました!』となったら、なんだか痛快な感じがするのは私だけでしょうか。元気と勇気と希望がもらえた、そんな話題でした! サムライオークションの骨董・古美術ファンの皆さまも、ぜひ物置の探索や身近な骨董の再評価をしてみましょう!