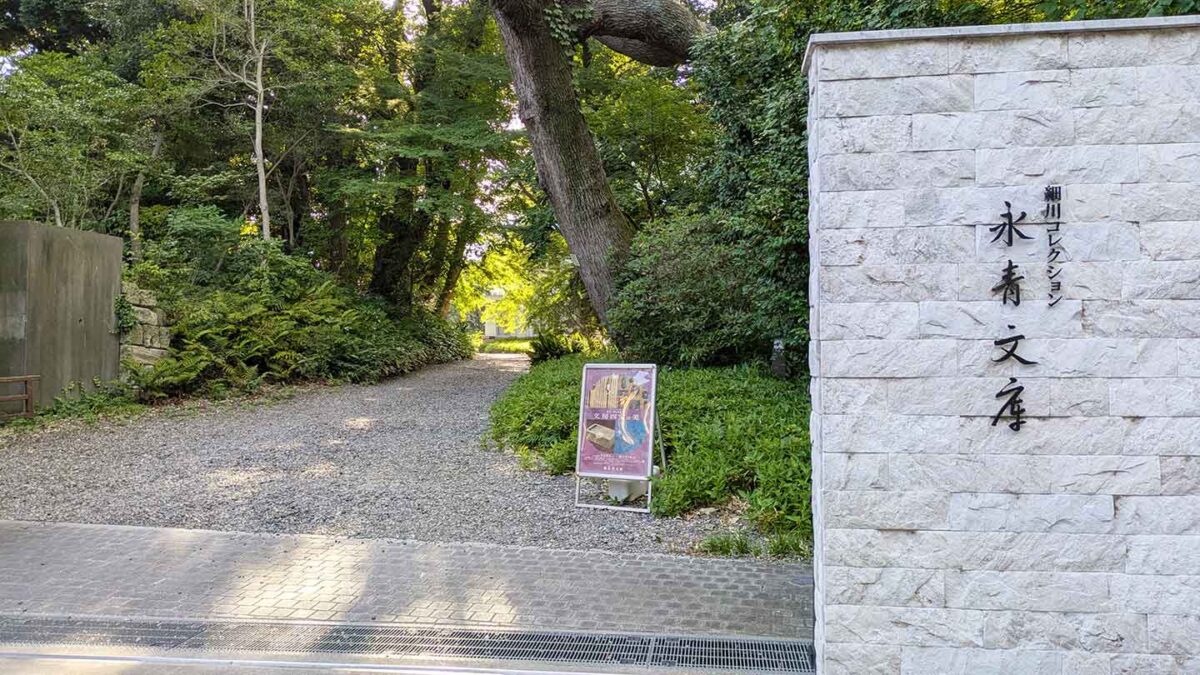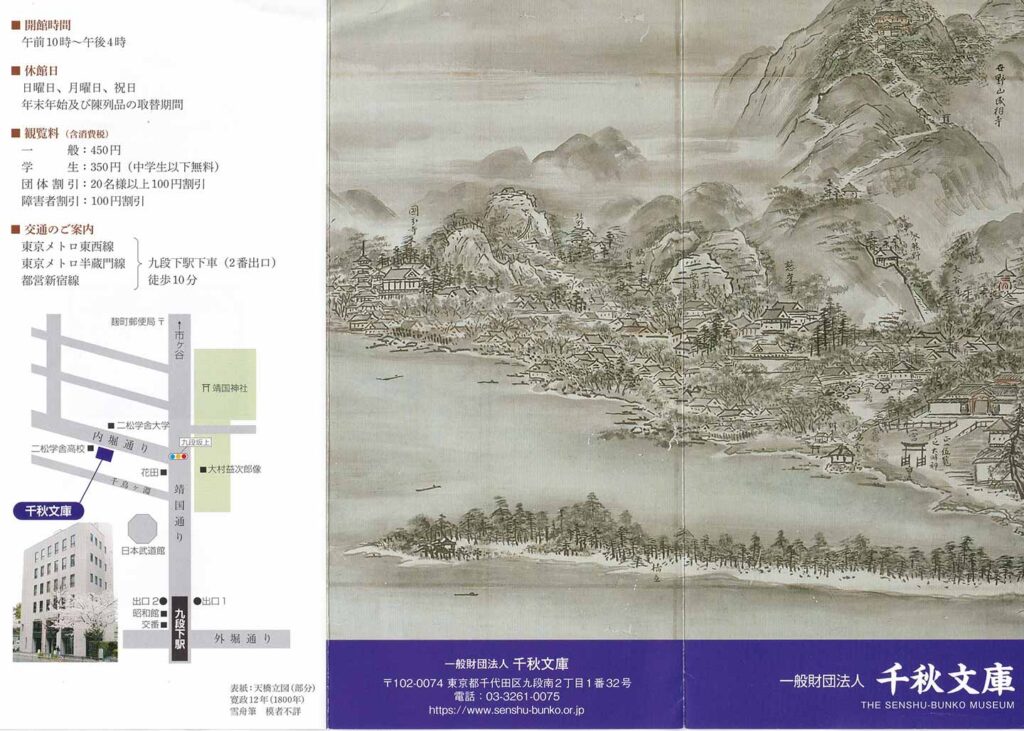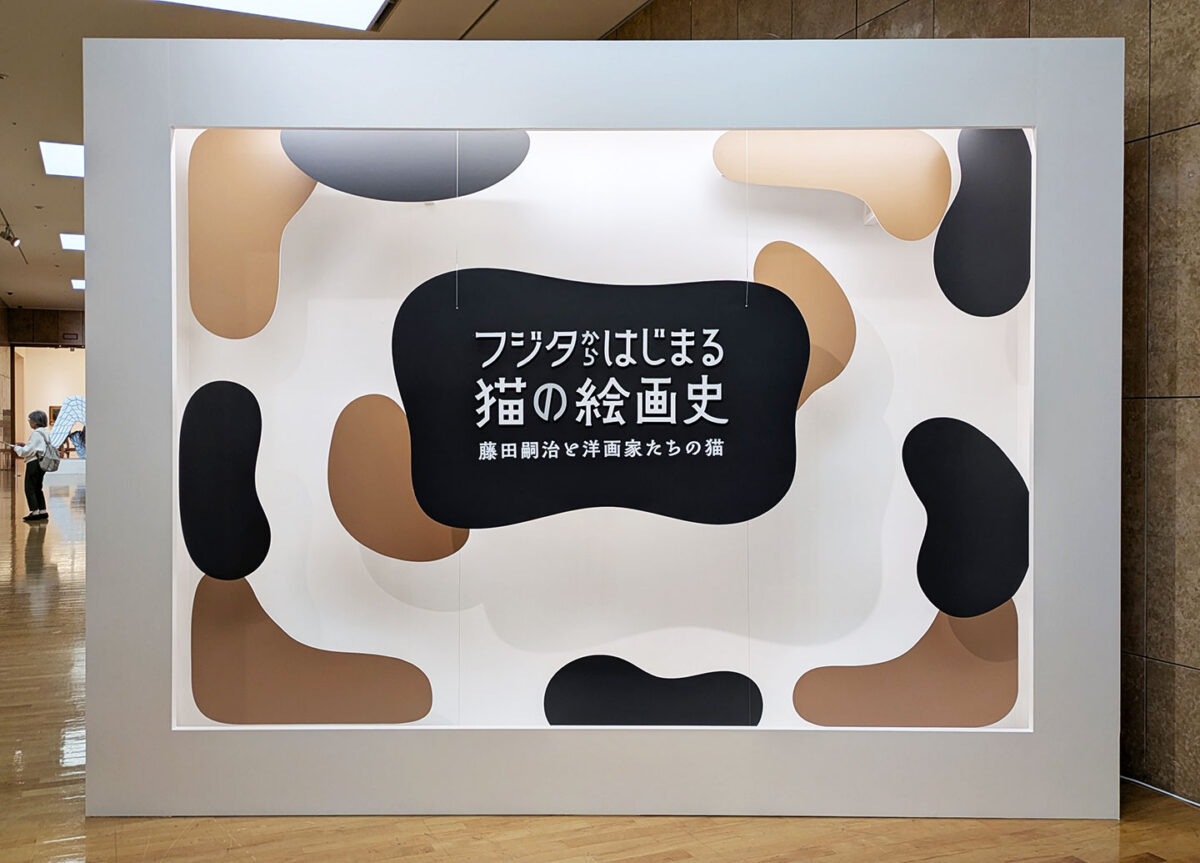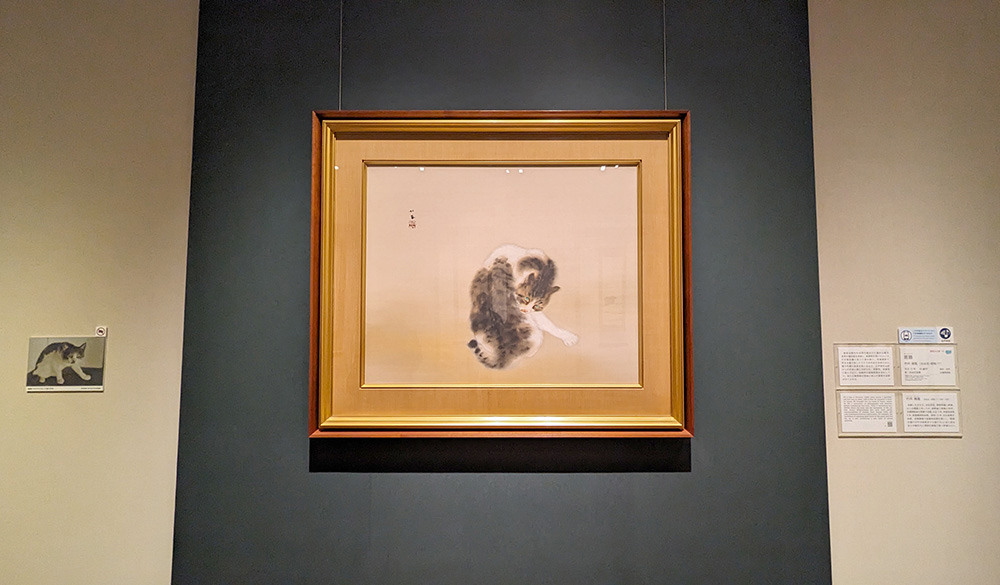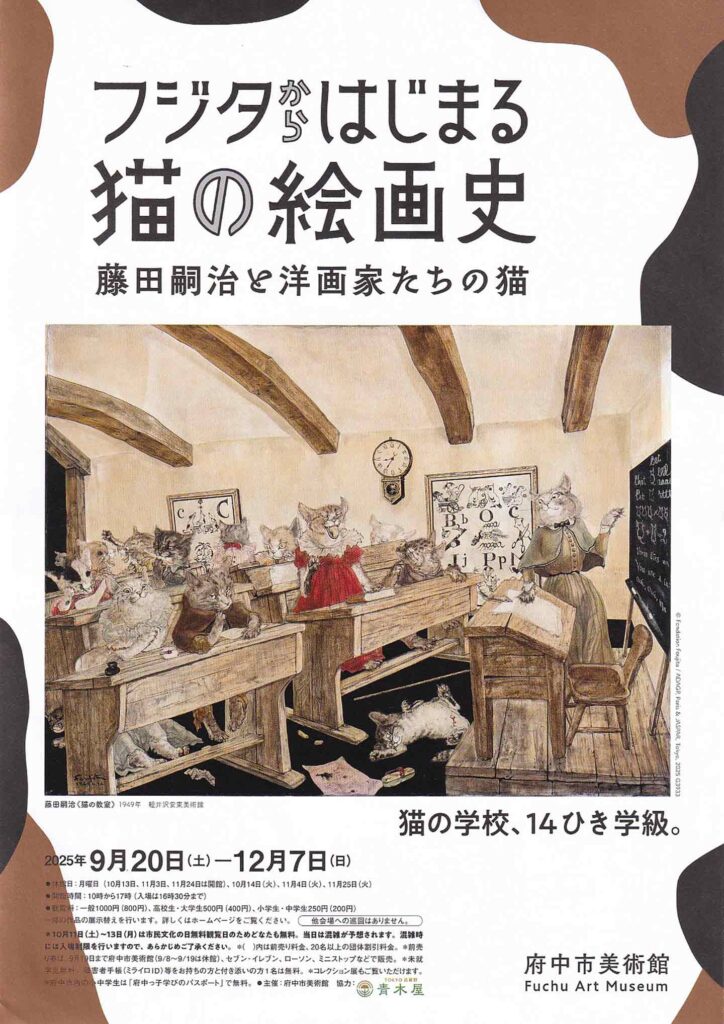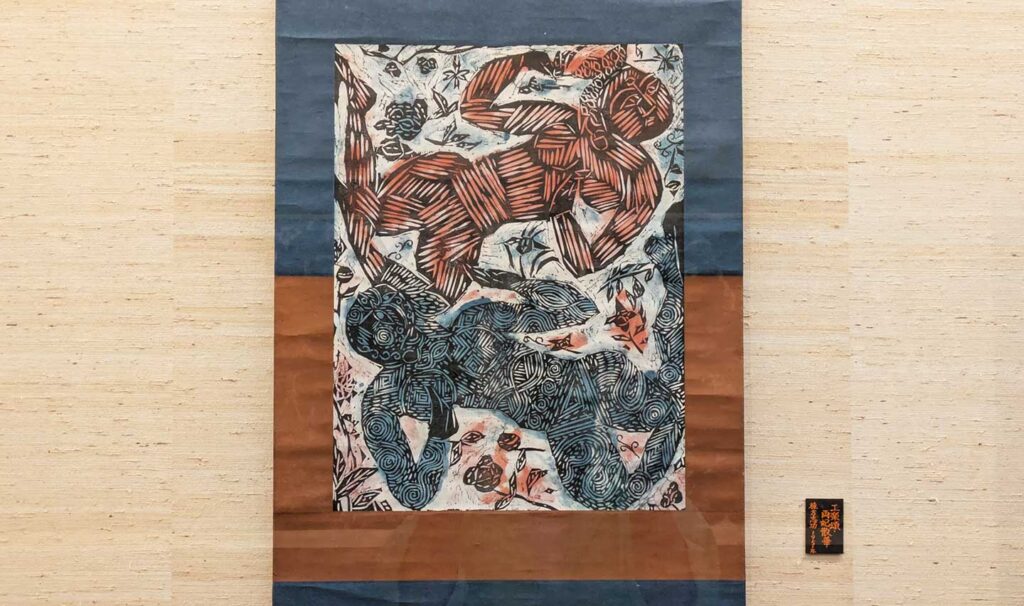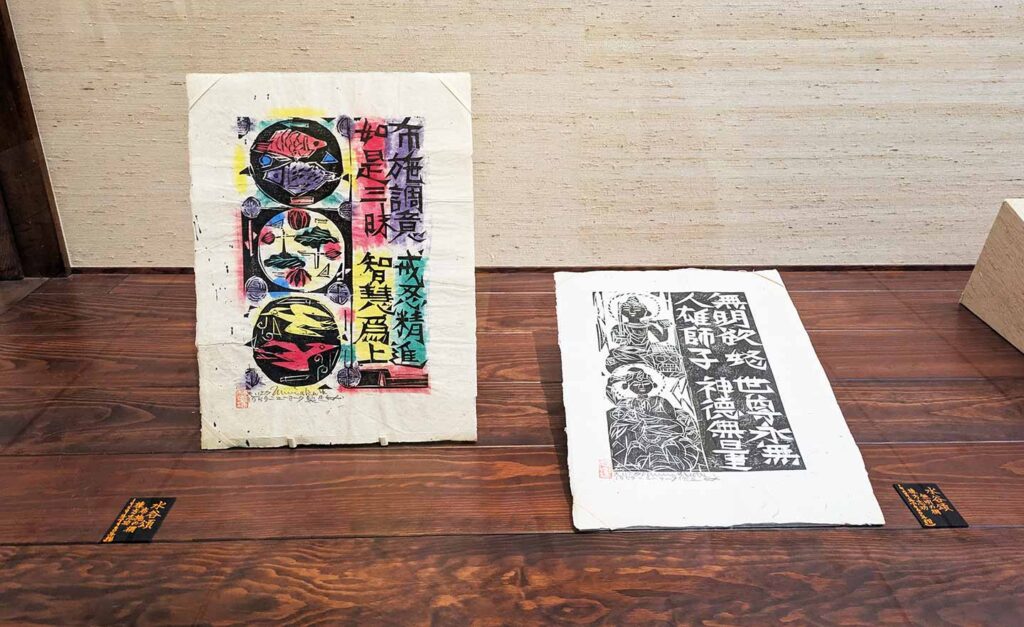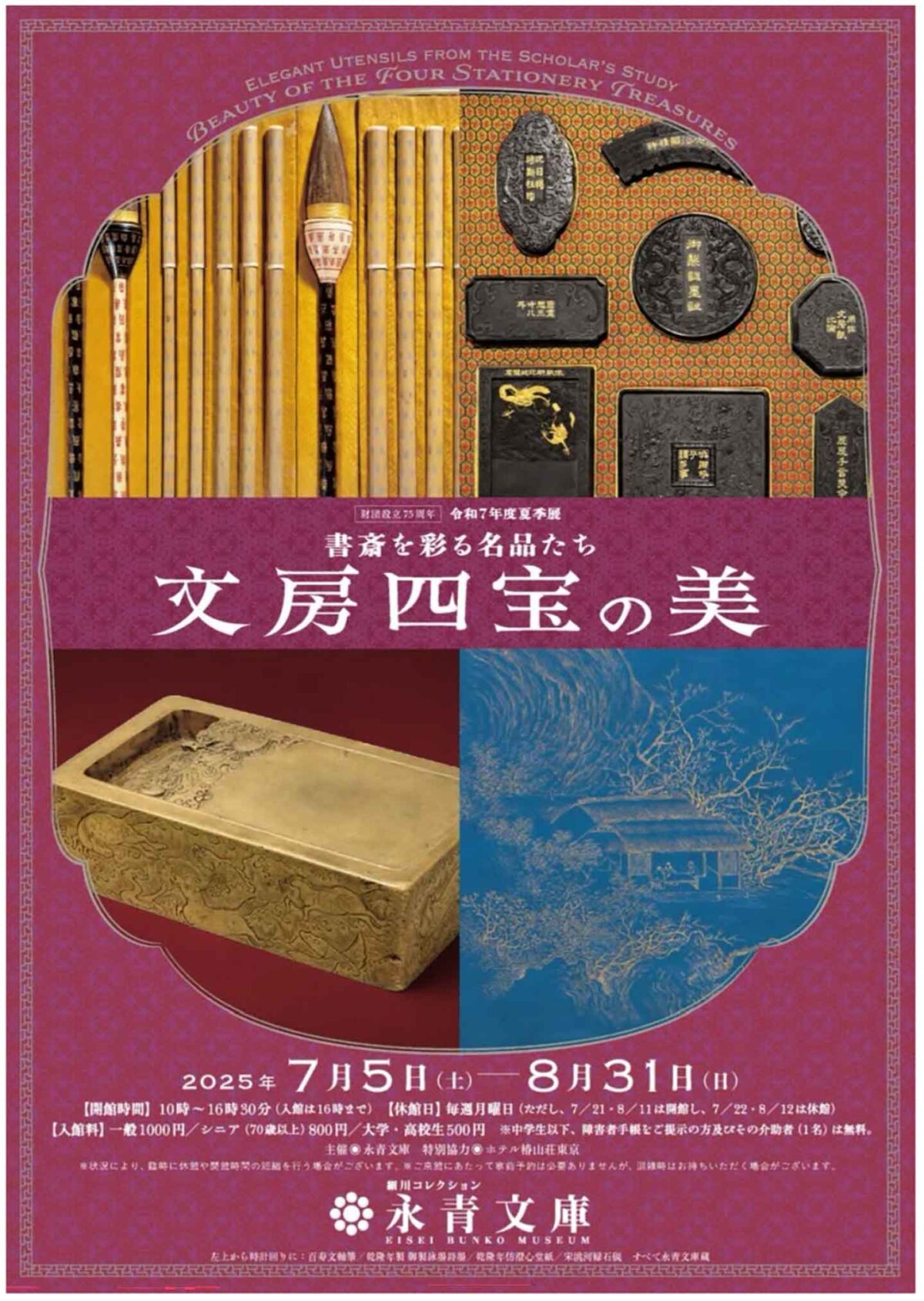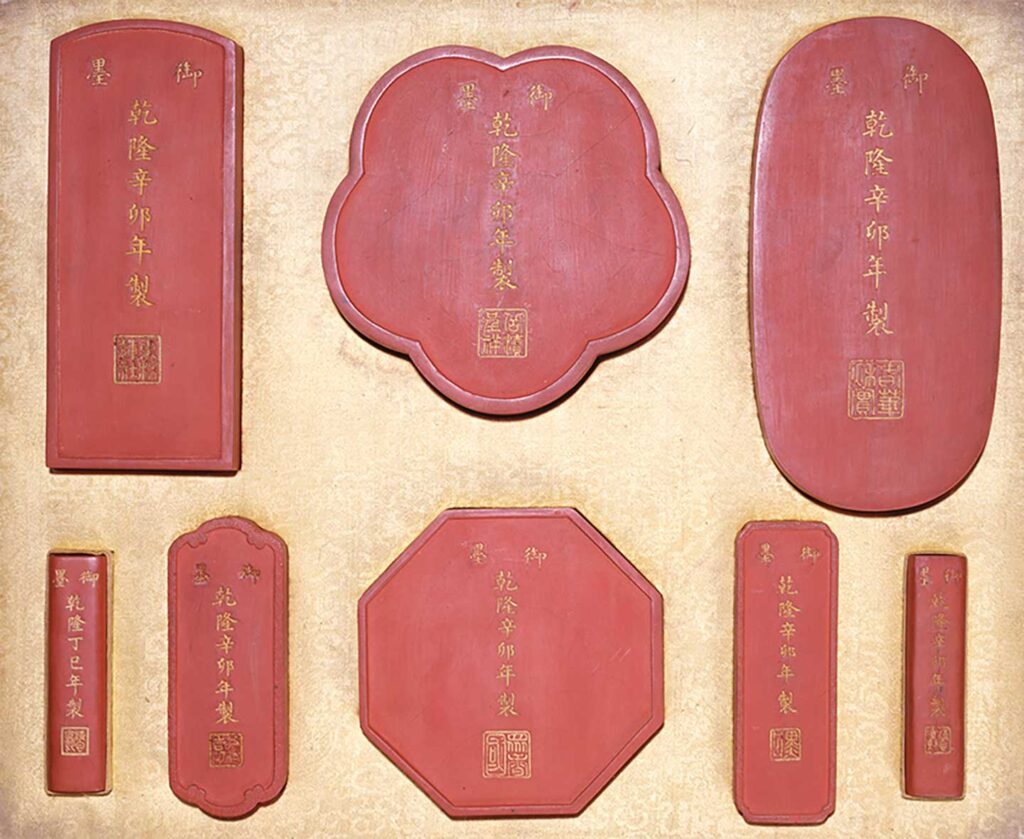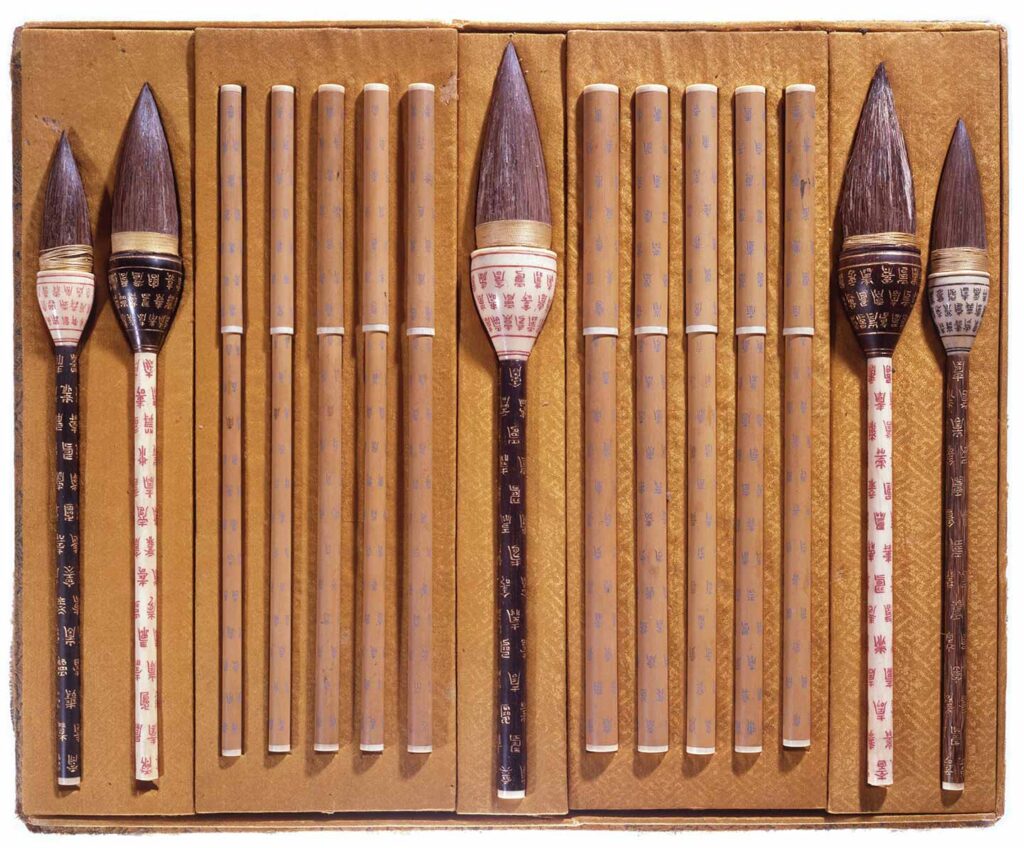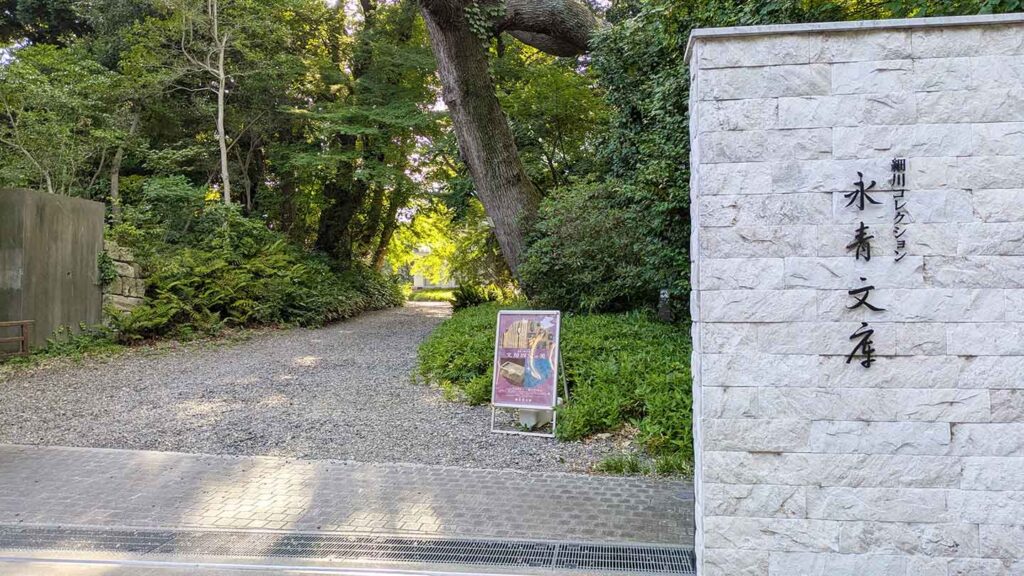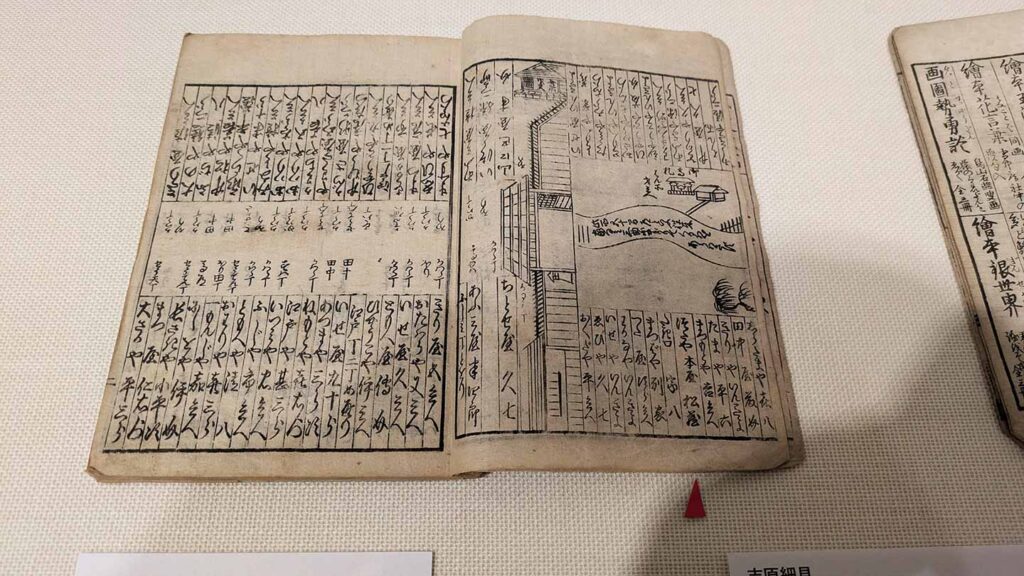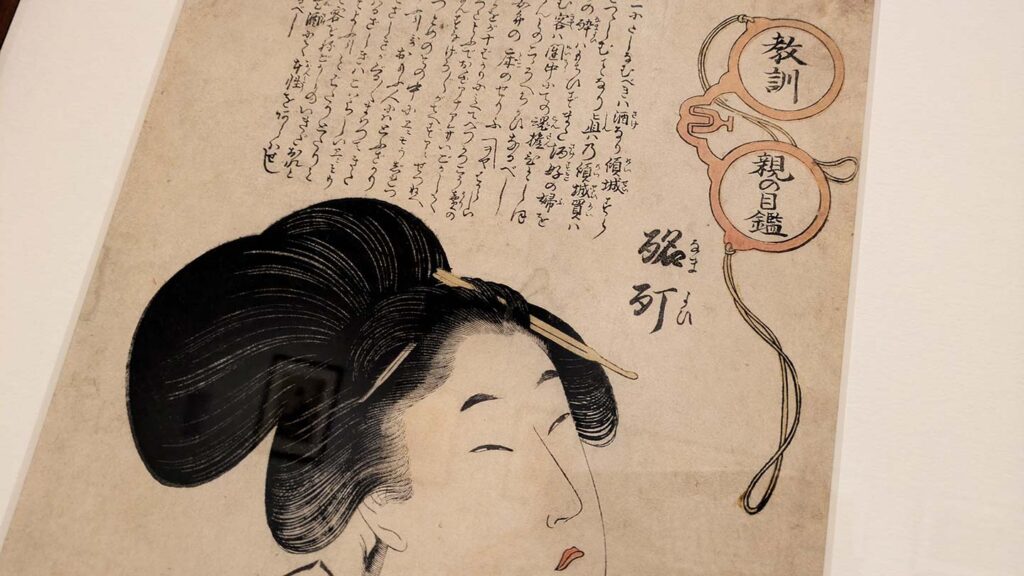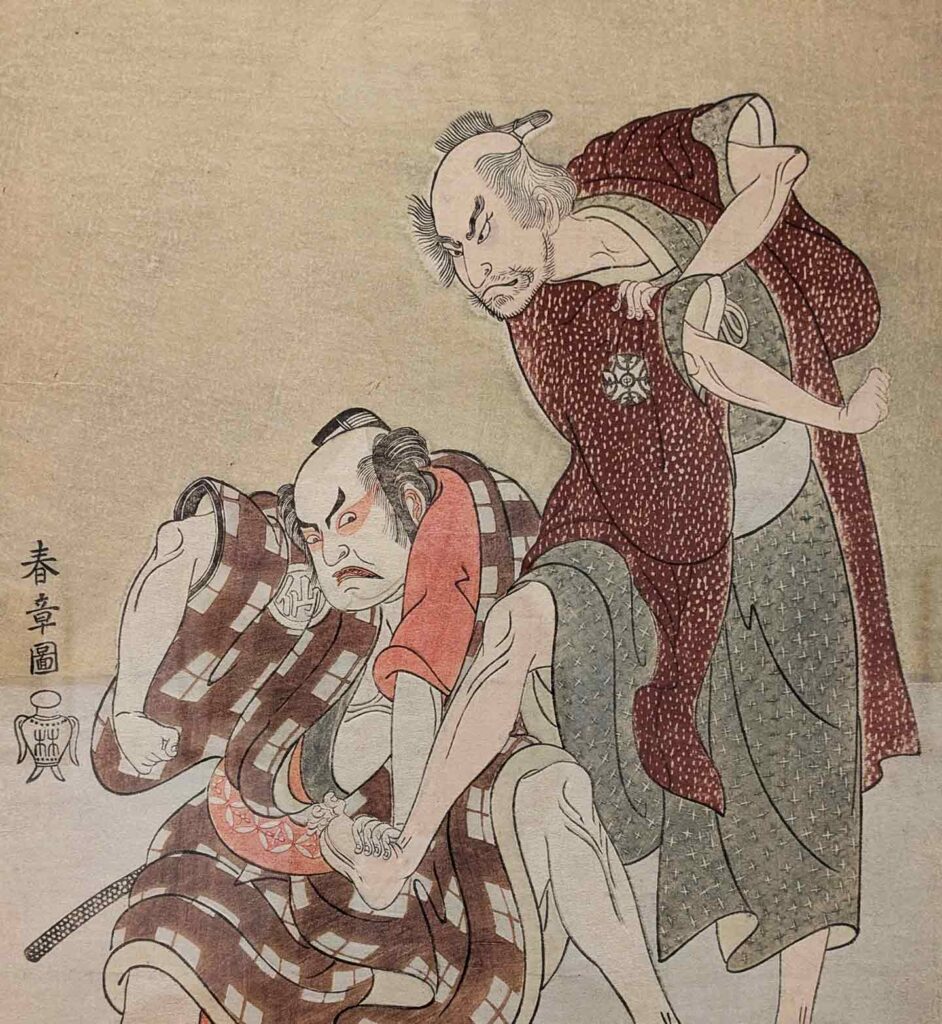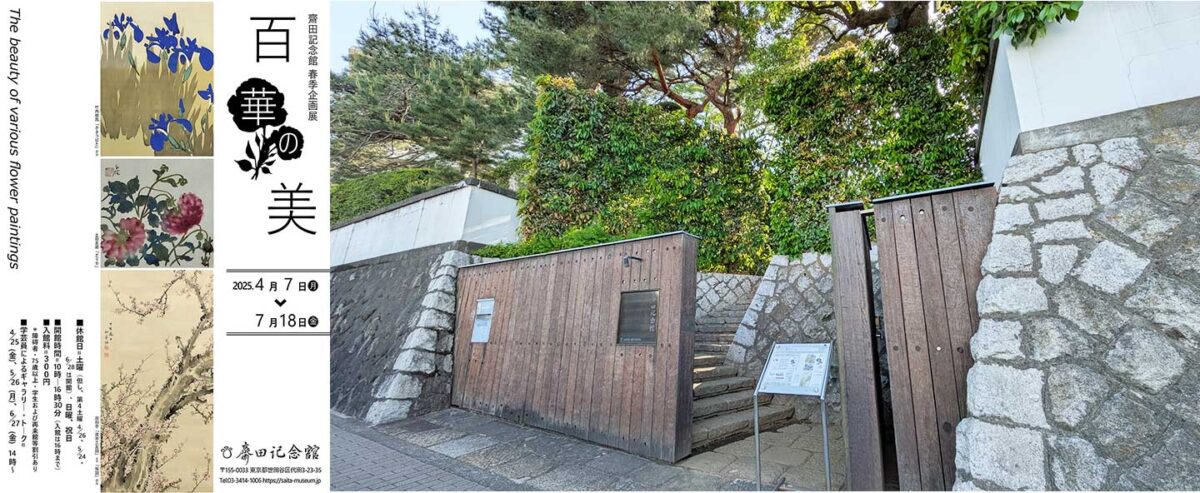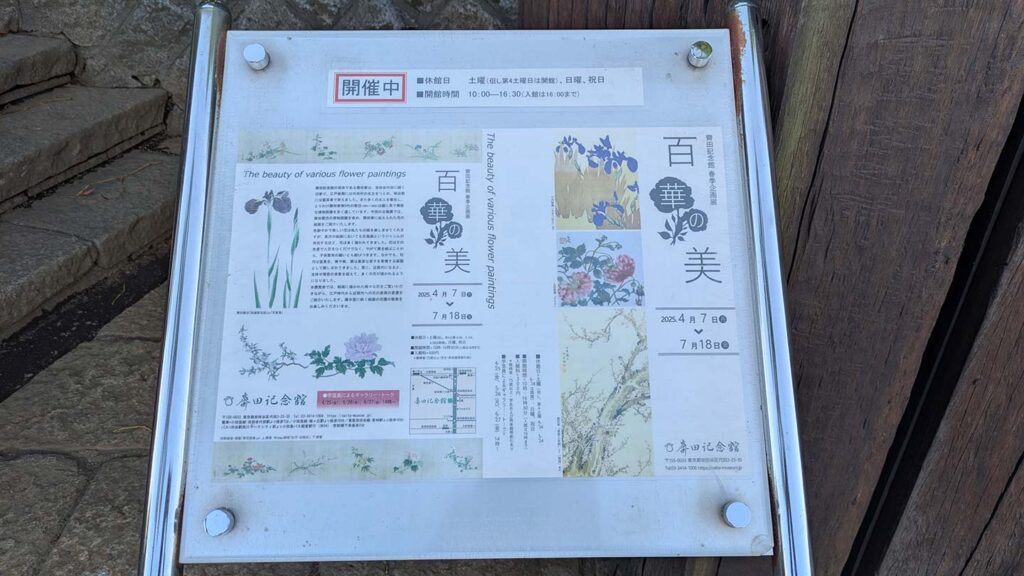あけましておめでとうございます。サムライオークションのブログをご覧くださり、ありがとうございます。2026年もオークションサイトに並ぶ美術品に関する美術展や情報をお届けしてまいります。
さて、新年一発目のブログは、本オークションで扱う美術品のなかでも特に人気の「刀剣」について。東京都渋谷区の明治神宮内にある〈明治神宮ミュージアム〉では、『明治神宮の刀剣』と題し、同神宮に奉納されている優れた刀剣の展示が行われています。
日本では、刀剣は古より神への祈りや感謝の意を込めた奉納品として捧げられてきました。『日本書紀』によると、第11代・垂仁天皇が、即位25年に武具を神に供えることを神官に占わせると「吉」と出たことから、弓矢や横刀を各地の神社へ奉納。さらに同39年には五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこのみこと)に命じて一千本の剣を造らせ、石上神宮(現・奈良県天理市)へ奉納したと記されているのだとか。
このように、神への刀剣の奉納の始まりは垂仁天皇の御代に始まり、今の時代にも引き継がれています。

愛刀家にはたまらない⁉ 刀匠の名刀がずらり
展示会場内に入ると、まず目に飛び込んでくるのは明治天皇と昭憲皇太后の御尊影。イタリアの版画家・画家のエドアルド・キヨッソーネが描いたものです。ちなみに、明治天皇は愛刀家として知られていますが、刀剣目録を御手元に置き、御座所にてたびたび刀剣鑑賞を楽しんでおられたのだそう。
今回展示されている刀剣は、南北朝~室町時代、江戸~令和に制作されたものなどさまざま。南北朝~室町時代に制作された大太刀(無名)は全長155センチもあり、どんな猛者が太刀を振るっていたのか、想像がふくらみます。
遺跡から発掘された太刀を模した源秀明謹製の鐶頭太刀や、藤原兼先(因州兼先)、藤原氏正、藤原兼房が手がけた太刀や刀もずらり。古い刀剣でも丁寧に研がれており、刃文の美しさが際立ちます。
また、鎌倉時代から山形県月山を拠点に活動し、現代にもその系統が残る月山鍛冶。宮内省御用刀匠となった月山貞一や、月山貞勝が作刀した刀も展示されています。また、2022年に明治天皇百十年祭を記念し、宝物殿にて奉納鍛錬が行われた、大阪月山家の5代目・月山貞利刀匠謹製の刀も拝見することができます。
ほかにも、勝村正勝、桜井正次(卍正次)、菅原包則、栗原昭秀など、さまざまな刀匠の名刀が。刀工の名前を見て歓喜する人もいるのでは?
本展の開催は2026年3月8日(日)まで。明治神宮に詣でつつ、ミュージアムにも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
Information
明治神宮の刀剣
会期:2025年12月20日(土)~2026年3月8日(日)
会場:明治神宮ミュージアム(東京都渋谷区代々木神園町1-1)
開館時間:10時~16時30分(入館は閉館の30分前まで)
休館日:木曜
入館料:一般1000円、高校生以下・団体900円
※小学生未満無料(保護者の同伴が必要)
リンク:明治神宮ミュージアム 公式サイト