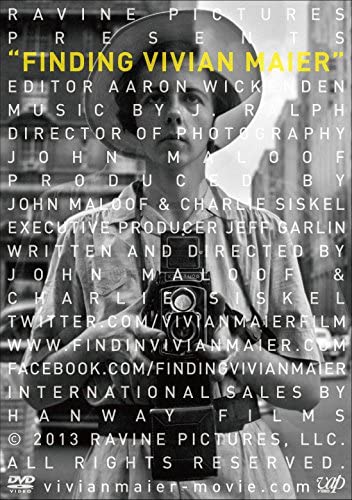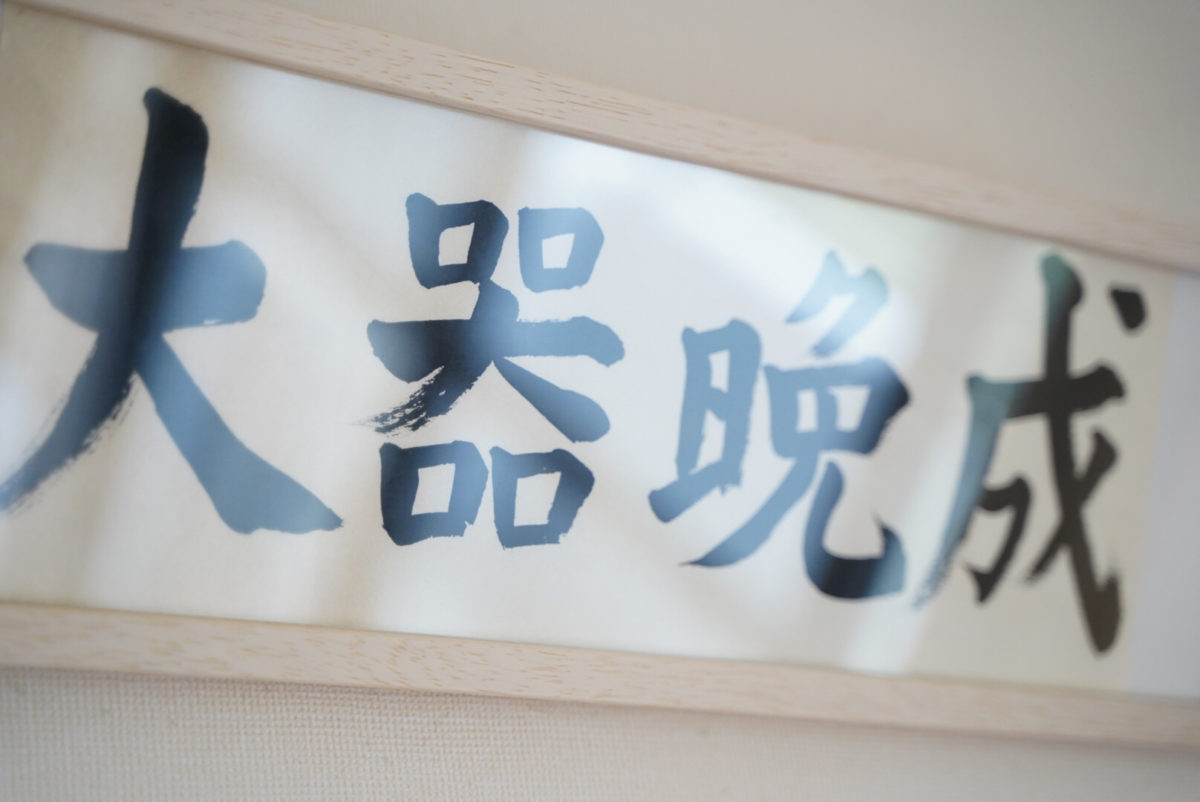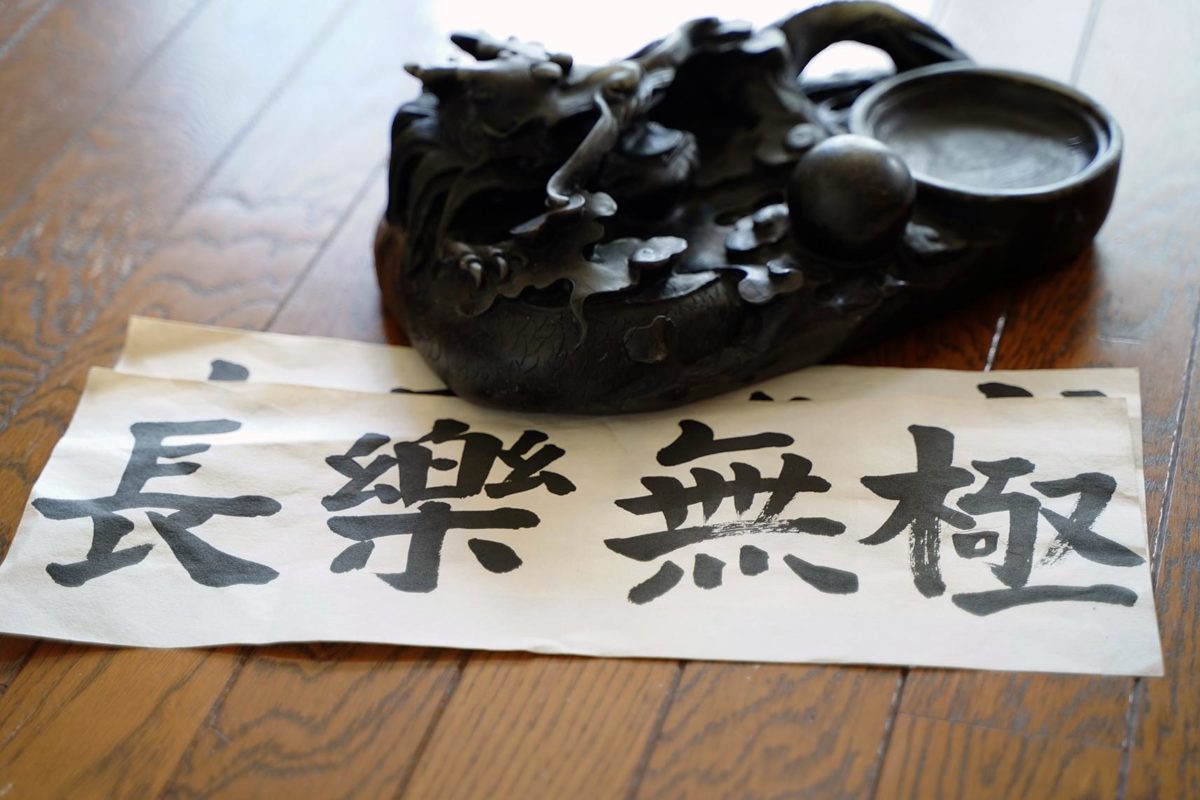こんにちは! 初心者大歓迎の《骨董・美術品専門のオークションサイト》サムライオークション、スタッフの利休です。
先週末、大江戸骨董市に行ってきました。感染者が増えてきている中、どのくらいの人出になるんだろうと思っていたのですが、やはり通常時に比べると少なめの人出でした。
でも、見て回る側からすれば、ちょうど良い混み具合。出店者さんは、ほぼほぼ会場いっぱいでしたので、道具系と陶磁器を中心に朝からお昼過ぎまで、たっぷり楽しむことができました。
改めて思いましたが、骨董市とかフリーマーケットは、老若男女が自然に出会える場所ですね。気の良い出店者さんですと、品物の善し悪しの見分け方なんかを丁寧に教えてくれます。全体の印象として、女性と若い方が増えているような気がして、少し嬉しかったですね。
ところで、目の前で積極的にお財布を開けていたのは、30代くらいの若い女性が多かったです。前々から感じていたのですが、女性の方がファッションとかライフスタイルに対して、自分らしさをしっかり自覚している人が多いですね。お化粧と関係があるのではないかと想像しているのですが、自分のスタイルがある人は、市場でも骨董や古美術品との良い出合いが多くなると思います。
自分が気に入ったモノ、素敵だと思うモノと出合うためには、まず自分のスタイルが確立している必要があります。自分の好きなモノがどういうものかわからない人には、良い出会いはなかなかありません。骨董・古美術品に興味を持った時、何か好きだなと思った対象が出てきた時には、その対象のどこに魅力を感じたのか、考えて書き出してみましょう。
沢山の品物を見て、気に入ったらその理由を考えてみる。そんな風にして経験を積んでいくことが、目利きになるということだと思います。私もまだまだ勉強中です。 サムライオークションにも、ぜひ遊びに来てください。あなたのための良い出合いを見つけてください。